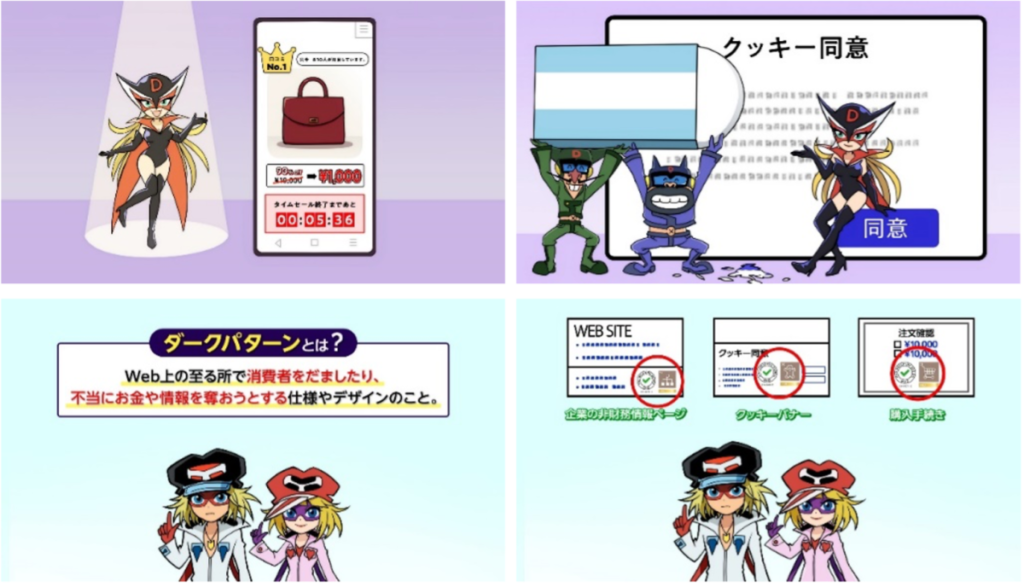中古車を購入する際、価格や車種と並んで重視されるのが「信頼性」だ。特にメーカー系販売店と異なり、地域密着で運営する独立系中古自動車販売店は、知名度や資本力の面で不利な立場に置かれやすく、顧客の安心感をどう確保するかが競争力の鍵となる。
近年はSNSや口コミの普及により、接客やアフターサービスの質が瞬時に共有される時代となった。説明不足や小さな不備が評価を左右する一方、来店数の伸び悩みや利益率の低下など、集客面の課題も深刻化している。限られた人員と予算の中で、接客品質や保証制度の明確化など、差別化に向けた取り組みが求められている。しかし現場では、属人的な対応や説明のばらつきが依然として残り、成果に結びつきにくい現状もある。こうした背景や販売店の実情を把握することは、業界全体の方向性を考えるうえで重要だ。そこで今回、埼玉県中古自動車販売商工組合 JU埼玉(https://ju-saitama.com/)は、中古自動車販売店の経営者・販売担当者を対象に、「中古自動車販売店の販売戦略と課題」に関する調査を実施した。
「来店数が伸びない」中古車販売店の集客ジレンマ

調査によると、「販売促進活動において感じている課題」として最も多く挙げられたのは「来店数が思うように増えない」(41.7%)だった。続いて「利益が出しづらく、販売単価が下がっている」(39.3%)、「WebサイトやSNSでの集客がうまくいっていない」(33.2%)が上位に並ぶ。いずれも事業基盤を揺るがしかねない内容であり、従来の手法では十分な効果を得にくくなっている現状が浮き彫りになった。
販売促進のために過去3年間で実施された施策としては、「自社ホームページやSNS(Instagram、LINEなど)の更新強化」(38.0%)が最多で、「折込チラシ・地域情報誌など紙媒体での広告展開」(30.2%)、「店頭POP・のぼり・季節イベントの実施」(28.6%)が続く。デジタルと紙媒体の両方を活用し、情報発信の幅を広げようとする動きが見られる一方、成果は必ずしも十分ではない。特にSNSを含むWeb施策が紙媒体よりも多く実施されていることから、オンラインでの接点拡大の必要性は現場でも認識されているといえる。しかし同時に、地域密着型販売店ならではの強みを活かすべく、紙媒体や店頭施策も根強く続けられており、デジタルとアナログの間で試行錯誤が続いている状況だ。こうした施策の分散は、限られた人員や予算をさらに圧迫し、結果として集客効果の鈍化につながっている可能性もある。
購入後のトラブルと対応体制の実態

調査では、販売店が購入後に受けるトラブル相談件数についても明らかになった。最も多かったのは「月1〜3件程度」(50.9%)で、次いで「4〜9件程度」(21.2%)、「0件(特に相談なし)」(19.8%)、「10件以上」(8.1%)と続く。半数以上の店舗が毎月複数件のトラブル相談に対応しており、販売後のアフターケアが業務の一部として定着している様子がうかがえる。
問い合わせの内容では、「購入後の不具合・故障に関する相談」(38.4%)が最多で、「保証の内容や適用範囲に関する質問」(33.4%)、「車体や内装のキズや汚れに関する相談」(32.7%)が続く。いずれも車両の状態や保証条件に関するものであり、購入前の説明不足や認識の齟齬が背景にある可能性が高い。
トラブル発生時の対応体制については、「担当営業がアフターサービスも兼任して対応」(43.0%)が最も多く、「整備スタッフ担当が対応」(23.8%)、「経営者・店長が直接対応」(22.0%)がそれに続く。営業担当が一貫して顧客対応を行うことで信頼関係を維持する効果もあるが、専門知識の不足や時間的制約によって対応の質やスピードに差が出るリスクも抱えている。
保証説明の温度差が生む、見えないトラブルの種

購入前の保証説明方法には大きなばらつきが見られる。「書類を作成し、口頭でも丁寧に説明」(43.2%)とする店舗がある一方、「書類は作成せず口頭で簡潔に説明」(37.2%)や「書類のみで説明なし」(14.6%)、「書類も説明もなし」(5.0%)といった簡略化傾向も一定数存在する。こうした説明方法の差は、顧客の誤解や不満、さらには購入後のトラブル発生につながる要因となり得るため、説明体制の均質化は急務である。
実際、購入後のトラブルを未然に防ぐため、各販売店ではさまざまな取り組みが行われている。最も多かったのは「納車前点検や整備内容を標準化しチェック体制を整えている」(46.3%)で、次いで「故障やリスクに関する注意点を事前に説明している」(43.5%)、「保証制度(有料)を標準で付帯している」(27.6%)が続いた。点検や整備の工程を統一し、車両の状態を可視化することは、不具合の早期発見や対応精度の向上につながる。また、使用上の注意点やリスクを事前に伝えることで、顧客との認識の齟齬を減らし、トラブルの予防効果も期待できる。一方で、保証制度の標準化は導入率が3割弱にとどまり、コスト負担や顧客理解の難しさが導入の壁となっている可能性がある。さらに、制度を導入しても説明方法や契約内容が統一されていなければ、逆に誤解を招きかねない。つまり、トラブル防止には「物理的な品質管理」と「情報提供の質向上」を同時に進める必要があるが、人的リソースや教育体制の制約が現場での実行を難しくしているのが現状だ。
価格競争から信頼競争へ、顧客が選ぶ理由の変化

メーカー系中古車販売店との差別化に向け、各店舗が今後強化したいと考えているポイントとして最も多かったのは「スタッフの接客力や説明のわかりやすさ」(43.4%)であった。続いて「支払総額表示など価格の透明性」(39.9%)、「保証制度やアフターサービス対応の品質・スピード」(37.8%)が挙がり、単なる価格競争ではなく、顧客接点の質を高める方向性が重視されていることが明らかになった。

特に、保証制度や販売店舗・営業担当を認定する制度については、その効果を「よくある」(27.1%)または「ときどきある」(50.6%)と回答した割合が合わせて約8割に達している。多くの販売店が、こうした制度が集客や購入の決め手になると実感しており、顧客にとっても信頼を裏付ける要素として機能していることがうかがえる。さらに、第三者機関による制度活用に関しては「非常に重要で、すでに活用している」(30.1%)、「必要性を感じ、今後活用を検討している」(46.8%)が大半を占め、導入済みまたは前向きに検討している店舗は約8割に上った。外部による評価や認定は、メーカー系販売店と比較しても遜色ない信頼性を提供できる手段であり、独立系販売店にとっては競争力を高める有効な選択肢となっている。
こうした「信頼の可視化」は、価格や在庫だけでは差がつけにくい市場環境において、店舗の存在感を高める戦略の中核となりつつある。顧客が「誰から買うか」を重視する今、制度活用と接客品質の向上を組み合わせた差別化戦略が、今後の生き残りを左右するだろう。
調査概要:「中古自動車販売店の販売戦略と課題」に関する調査
【調査期間】2025年7月11日(金)~2025年7月15日(火)
【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査
【調査人数】1,006人
【調査対象】調査回答時に中古自動車販売店の経営者・販売担当者と回答したモニター
【調査元】埼玉県中古自動車販売商工組合 JU埼玉(https://ju-saitama.com/)
【モニター提供元】PRIZMAリサーチ
今回の調査は、中古自動車販売店が直面する現実的な課題と、その解決に向けた方向性を浮き彫りにした。来店数の伸び悩みや利益率の低下といった集客面の停滞、販売後対応の属人化、保証説明のばらつきはいずれも顧客満足に直結する要素であり、放置すれば信頼低下につながる危険性が高い。限られた人員や予算の中でも、接客品質の底上げ、情報提供の標準化、そして第三者機関制度の活用といった取り組みは、店舗の競争力を左右する不可欠な要素である。
中古車市場は、価格や在庫数だけで差別化できる時代を過ぎた。消費者は「誰から買うか」「どんな対応を受けられるか」を重視し、信頼できる販売店を選ぶ傾向を強めている。こうした市場環境の中で生き残るためには、信頼の可視化と接客品質の向上を両輪とする戦略を築き、顧客に「安心して選べる理由」を提示し続けることが求められる。中古自動車販売は、今まさに信頼を軸にした競争時代へと突入している。